自動車メーカーは、何故「50:50」に拘るのか考えてみました。
前回の記事でも書きましたように、コーナリングに於いてはスリップアングルの付き方が重要なポイントになります。
前・後輪の荷重割合を「50:50」にすれば前後同じタイヤサイズで、同じスリップアングルが得られ、スムースな旋回が出来る訳です。
FF車であるMINIは、重量配分が前輪に大きく掛かっているため、スムースな旋回にはタイヤに対して配慮が必要になります。
旋回のメカニズムは次のような流れになっています。
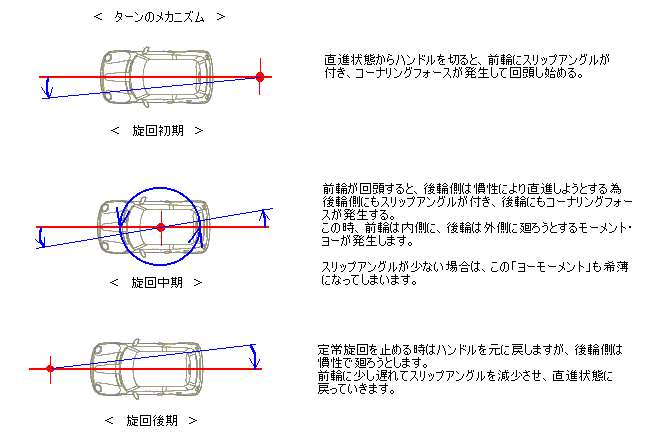
- 直進状態からハンドルを切ると、前輪にスリップアングルが付き、コーナリングフォースが発生して回頭し始める。
(スキーでいう「回頭」)
- 前輪が回頭すると、後輪側は慣性により直進しようとする為後輪側にもスリップアングルが付き、後輪にもコーナリングフォースが発生する。
この時、前輪は内側に、後輪は外側に廻ろうとするモーメント・ヨーが発生します。
(スキーでいう「回旋」)
スリップアングルが少ない場合は、この「ヨーモーメント」も希薄になってしまいます。
- 定常旋回を止める時はハンドルを元に戻しますが、後輪側は慣性で廻ろうとします。
前輪に少し遅れてスリップアングルを減少させ、直進状態に戻っていきます。
「コーナリングが楽しい!」、「運転が楽しい!」ということは、この「ヨー・モーメント」の感じ方ではないでしょうか?
最近のスキーでのカービングターンは以前のスキッドターンと比較しますと、廻っているという感覚が強く、その動作に快感を覚えます。この廻るという感覚が「ヨー」なのです。
車の場合、前輪に頼った運転ではなく、後輪を上手く使ってあげることで、初めて「ヨー・モーメント」が発生します。(前輪の磨耗が多い時は、運転の仕方を省みることも必要です。)
自動車メーカーはロープロタイヤやRFT(サイドウォール補強型)などスリップアングルの発生し難いタイヤを標準設定しているため、アクティブ・リアサスなどを造り出し「ヨー・モーメント」の演出に苦労しています。
今こそ、タイヤの基本性能を再確認・再認識する時ではないのかな?と思ってしまいます。
以前の「Pilot Preceda」では希薄であった「ヨー」ですが、今回の「DNA S.drive」 は同じタイヤサイズながら、それを適度に感じとることが出来き、とても楽しいタイヤです。
◆ 同じ曲がるものでも、スキーではこんなにも考えています。
|